観光スポット
カテゴリやエリアで検索しよう!
カテゴリやエリアで検索しよう!
大正建築のレトロなレンガ作りの建物とアートが融合
県指定重要文化財「旧妹尾銀行林田支店」の美しい建築を活用し、芸術文化の創造・発信拠点となるアートギャラリーとして整備されました。銘木が使われている木造本館や赤レンガ倉庫など大正時代の重厚な空間を体感しながら、展覧会を通じて多彩なアートに触れることが…

早島に伝わる花ござ手織り技術を学ぶ
早島伝統の花ござ手織り技術を保存継承する伝承館。手織り機を用いた花ござの制作のほか、ミニ機を用いて地元の小学生などに手織りの体験教室を開催しています。

県下三大巨石古墳の一つで、内部にある石室は、巨大ないくつもの石を精密に組み合わせた横穴式の大空間で、入口の羨道とその奥の玄室に分かれています。6世紀後半の築造と考えられており、直径54m、高さ7mの円墳です。

曹洞宗の寺院。廃寺状態だったこの寺の復興のため、現住職の岩垣正道(しょうどう)さんがはじめた趣味の版画を襖に貼ったのをきっかけに、今では襖絵、天井絵、掛軸など約300点あまりを展示し「版画寺」として有名になっています。日本だけでなく、ロンドンやニュー…

池に映える朱色の鳥居と紅葉が美しい
創建は奈良時代は天平勝宝年間、この地で山岳修行をしていた報恩大師によるものとされています。雨乞いの神である竜神様、八大龍王と、豊作の神であるお稲荷様、最上稲荷が渾然一体となった民間信仰の霊場でした。宗派は、かつて天台宗であった時期があり、日蓮宗に改…


SANAAが初の木造個人住宅として設計したもので、後にSANAAから独立した建築家、周防貴之が芸術家と建物を繋ぐ空間コーディネートと改修を行い、美術館へ転用されました。建築家/完成年:SANAA/1996年見学・撮影について:館内見学可能

先陣の功をあげた佐々木盛綱が修復し、源平合戦にまつわる古跡が数多く残されています。また、藤戸寺には鎌倉時代中期の石造五重塔があるほか、初夏の頃には「平家物語」で有名な沙羅双樹の花が咲くことでも知られています。
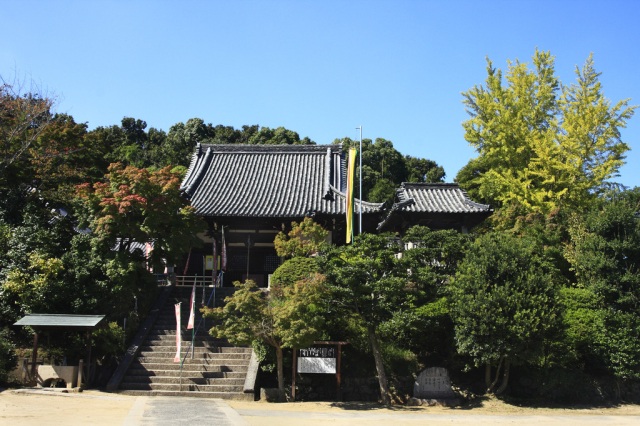
体のしくみについて学ぶ
現代の医学・医療に関することをわかりやすく展示してある、世界的にも珍しい博物館です。からだのしくみや、病気の予防などを、子どもから大人まで、クイズ形式やゲーム感覚で見学できます。展示はパネル以外にも、骨や臓器の模型、病院で使っている本物の医療器具(…

江戸時代に岡山藩で起こった「渋染一揆」に関する資料を展示
江戸時代に岡山藩で起こった「渋染一揆」に関する資料を展示する資料館です。

戦国時代に岡山の宇喜多勢と安芸の毛利勢がこの地で激突した際、宇喜多勢の総大将・宇喜多与太郎基家は足を失傷し竹やぶへ隠れましたが、村人が探索の武士に居場所を教えたため、与太郎は捕らえられました。その後、村人が与太郎へのおわびと供養のため、また足の悪い…
県下では珍しい扇の縄と呼ばれる型式で、城郭は扇を広げたように配置され、四段にわたって構築されています。築城時期は不明ですが、南北朝時代に今川氏、後に上田氏が城主となりました。天正3年(1574)に毛利氏の城攻めを受けて落城し、その後江戸時代初期に廃城と…
ベンガラは赤色顔料として宝永4(1707)年に吹屋で開発され、特産地として栄えました。ベンガラ館は明治の頃のベンガラ工場を復元したもので、当時の製造工程を紹介しています。

吉備中央町出身で日本を代表する庭園研究家である重森三玲を顕彰する記念館です。『永遠のモダン』ということばがよく似合う重森氏は、庭園学・作庭を独学で学び、日本各地に力強い石組と枯山水が特徴的な斬新な庭園を数多く残しています。記念館には「日本庭園史大系…

岡山県下最古の木造塔建築!
明徳年間(1350年頃)に真言宗の寺院になった長福寺は、奈良時代(757年)、唐の高僧鑑真和尚が開基したと伝えられています。当初は真木山(まきさん)の山頂にありましたが、度重なる火災により、昭和3年に寺院が、昭和26年に三重塔が現在の場所に移りました。高さ約…


おかやま山陽高校所有の海の家(通称ホワイトハウス)をイヌ小屋に見立てて造形家・川埜龍三(かわのりゅうぞう)が行う「犬島ハウスプロジェクト」。「犬島の島犬」はその一環として作られた奥行5m10cm×高さ3m×幅2m40cmの巨大な犬の彫像。犬島の番犬とし…

5世紀後半に造られた前方後円墳で、造山古墳(岡山市)、作山古墳(総社市)に次いで県内3番目の大きさを誇ります。墳丘の周囲は一部が埋没して水田化しているものの水をたたえた周濠(しゅうごう)が巡っており、農業用のため池として改修・再利用されてきました。現…

小堀遠州作の枯山水庭園が素晴らしい
頼久寺は足利尊氏が諸国に建立させた安国寺のひとつと言われ、庭園は国指定の名勝となっています。庭園は備中国奉行として当地に赴任していた小堀遠州が築いた枯山水で、遠州庭園の原点が見える庭として注目されています。江戸初期の完成で、桃山後期の特徴が表れてお…

国指定文化財
本堂と番神堂と中門は国の重要文化財に、三重塔と祖師堂は県の重要文化財に指定されています。また、小堀遠州作の見事な庭園や多くの文化遺産が残され、朝鮮通信使が宿泊した名刹にふさわしい格調が漂います。2017年10月には「朝鮮通信使に関する記憶」がユネスコの世…

広く美作地方一円の人々から古来より「学問の神」「書の神」として崇敬され、信仰を集めています。受験シーズンには合格祈願が毎年行われています。

樹齢100年以上、高さ約15m、枝張り幅約18mのしだれ桜は、見るものを魅了します。さくらの季節にはライトアップも行われ、大勢の人で賑わいます。

沼城は、天文初年頃に中山信正によって築かれた。信正は、金川城の松田氏、後に天神山城の浦上宗景に仕えた。永禄2年に宇喜多直家によって城は奪われ、直家は居城を新庄山城から沼城へと移した。直家はここを拠点に、備前・美作・備中へと勢力を拡大した。
812(弘仁3)年弘法大師の創建と伝えられる古刹で、江戸時代には、松山城主水谷氏の外護を受け、京都仁和寺の中本寺として栄えました。雲海がたなびく標高500mの山上にあり、平安時代の山岳仏教の姿を色濃く残しています。
池田家の菩提寺である京都花園妙心寺護国院の火災をきっかけに、池田光政が津田永忠に命じて作らせた岡山藩主池田家の墓所。山中にあり、光政の祖父輝政(姫路城城主)、父利隆、光政らを儒式で埋葬しています。輝政の「一のお山」を中心に、合計7つの「お山」で構成…

美作河井駅~知和駅間に架かる石造りの鉄橋で、その橋を通る列車との風景は鉄道ファンにとって絶好の撮影スポットです。

豊臣秀吉の正室ねねの実兄を藩祖とする木下家2万5千石の陣屋町
豊臣秀吉の正室・ねねの実兄を藩祖とする木下家2万5千石の陣屋町。保存地区は陣屋町のうちの町人町にあたります。足守の特徴として、格子が良好に保存されていることがあげられます。千本格子や親子格子など端正な格子が取り付けられ、生活の中から生み出された比例の…

江戸時代中期から後期にかけて、百二十石から百五十石取りで、近習役や番頭役などを勤めた武士の住宅である。江戸中期の建築として平屋建て、桟瓦葺き、箕甲・入母屋造りで大ぶりな三ッ花懸魚を取付け、玄関には幅二間の式台を設け、玄関の間の正面には一間半の棚を設…

明治43年に建築された旧総社警察署の建物です。現存する市内唯一の明治洋風建築で、八角形の楼閣風の入口が明治の雰囲気を漂わせています。館内には備中売薬や阿曽の鋳物、い草産業など、明治を中心とした伝統産業の資料が展示されています。

幕末(19世紀初めごろ)の洋学者である箕作阮甫の生誕地。阮甫は21歳で津山藩医となり、後に江戸に出て洋学を学んだ。カラフト問題でロシアと交渉した時の日記「西征紀行」はよく知られている。

森忠正公によって城下の守護神として造営された神社
聖武天皇の御代天平5(733)年の創祀と伝えられている神社です。当初は現在の津山市小田中の地にありましたが、天文8(1539)年火災に遭い社殿や宝物などことごとく焼失しました。慶長8(1603)年美作の国18万6500石の国守大名として入封した森忠政公(森蘭丸の弟)が…

国の重要文化財に指定された倉敷町屋の代表的な建築物
江戸時代に新田開発などで大きな財を成した大橋家が、1796(寛政8)年に建てた建物です。倉敷の代表的な町家のひとつに数えられ、長屋門や倉敷窓・倉敷格子などを備えた往時の商家の姿を現在に残す重厚な建築物です。

吉備平定のため派遣された吉備津彦命の射た矢と鬼ノ城にいた鬼神の温羅(うら)が投げた岩がぶつかり、ともに喰らい合い落ちたといわれる伝承がある社。温羅と呼ばれた鬼と吉備津彦命が戦った際に、温羅が投げた岩が吉備津彦命が射た矢とぶつかり、落ちた場所という言…

原子物理学の父ともいわれる仁科芳雄博士の遺品類に接するとともに、展示器材を通じ好奇心を養うことができます。

日本でも珍しい、ブリキ、陶器、鉄などさまざまな貯金箱の博物館です。犬の資料館やおもちゃ博物館も併設しています。

「石の島」北木島の観光拠点
笠岡諸島 北木島にある複合施設。石の歴史や文化、魅力を紹介する「ストーンミュージアム」や石雑貨から高級石製品まで揃った「ミュージアムショップ」、瀬戸内海の島々と青い空を眺めながら、ゆっくり流れる島時間を過ごせるカフェがあります。また、石灯りの製作体…

ベンガラの町の人の住まう活きた文化財
西江家は江戸時代、幕領における惣代庄屋で、代官御用所を兼ねた館である。自主的行政機構として吹屋地区の「民の暮らし」を統括。郷蔵・駅馬舎・手習い場・お白洲・役宅などが現在もそのまま保存されている。また、六代目西江兵右衛門が紅柄産業に着手、成功し、吹屋…

中世の美作の政治の中心地で、院庄の館(いんのしょうのやかた)だった国指定の史跡です。鎌倉時代の末頃、後醍醐天皇が隠岐に流される途中にこの館に泊まり、その際児島高徳が館の庭の桜の幹を削って十字の漢詩を書いて天皇を慰めたという故事により、明治2年に創建…

桜井宮覚仁親王と冷泉宮頼仁親王が、隠岐で亡くなった父君である後鳥羽上皇の一周忌供養のために、1240(仁治元)年に建立したものと伝えられています。

1658年(万治元年)、備中松山藩主水谷公が玉島港を開く際、干拓工事の成功を祈って出羽の羽黒神社を勧請した神社です。屋根の上には烏天狗の鬼瓦があり、今では町おこしのシンボルとなっています。
