観光スポット
カテゴリやエリアで検索しよう!
カテゴリやエリアで検索しよう!
那須与一が屋島の合戦の功績として与えられた荏原荘に、那須氏が地頭として来地後、菩提寺として開基したと言われています。境内には、与一が屋島の合戦で弓を引く際に破り捨てた片袖を祀ったという袖神稲荷があります。また、寺の北東の山中には与一を供養する五輪塔…
東アジア情勢が緊迫した7世紀頃に築造されたと推定されています。発掘調査の結果、土塁線や一の木戸等の水門、石塁構造が確認されています。

備中成羽藩成立時に入封した山崎家治の次男で、讃岐国丸亀から旗本として戻った山崎豊治が、菩提寺として建立した桂厳寺境内には、豊治以降の歴代領主の墓石や供養塔が整然と並ぶ。また、本堂には御霊屋も併設されるなど,近世大名墓の形態を示す貴重な史跡である。
閑谷学校創建時の瓦を焼くために設けられた窯跡です。窯は全長約9mほどの小窯2基と考えられています。のちにはこの窯を利用して祭器、茶器、細工物などの閑谷焼を焼いていました。現在は一部が宅地となっており、僅かに残る窯の側壁などに往時の面影を見出すことがで…
北房地域の歴史と民俗を展示する施設。国指定史跡の大谷1号墳から出土した遺物や、中世の刀鍛冶国重一党の名刀も展示されています。

産業関係では手延べそうめんの製造器具や戦前農家経済をうるおしていた麦稈真田の関係器具・室町時代に庶民の日用雑器を焼いた窯跡や町内で発掘された土器など展示しています。また、書画展示コーナーでは、鴨方町とゆかりの深い先人の作品を展示しています。
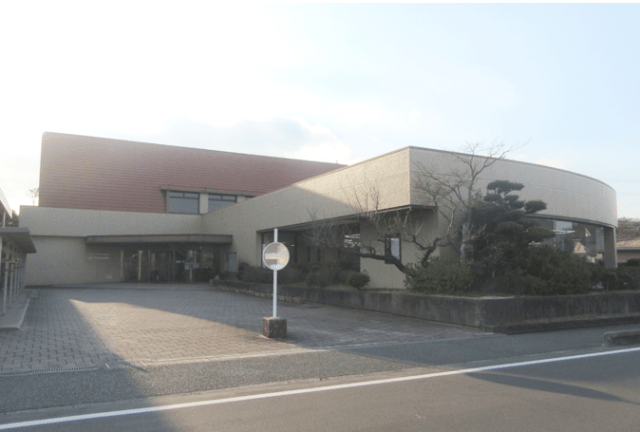
通称名は垪和郷一の宮(ハガゴウイチノミヤ)。一宮八幡神社の獅子舞は、県指定無形民俗文化財に指定されています。

江戸時代初期の元和4年(1618年)建築の入母屋造り、本瓦葺きの建物です。桃山時代の建築様式を伝える装飾に富んだ建物です。

赤磐市出身で日本を代表する女性詩人・永瀬清子の人と作品が紹介されています。遺族から寄贈を受けた蔵書や原稿、書画、書簡などの遺品が展示されており、隣接する熊山図書館では、清子の映像の視聴・著書や関連図書の閲覧もできます。

牛窓湾を廻る5基の大型前方後円墳の一つで、湾の西端の丘陵上にあり、墳長約55m。円筒埴輪その他副葬品が多数出土しています。
前方後円墳。墳頭には約2m×0.9mの家形石棺が剥き出しの状態で置かれています。1907年(明治40年)に鏡、刀、勾玉、管玉などが多数発見され、現在は東京国立博物館に収蔵されています。

丘陵の斜面を整地して造営された下道氏の墓地。ここから和銅元年(708年)の銘文のある銅製骨蔵器等が発見され、奈良時代の墓制を知ることができる貴重な遺跡とされています。
平安中期、村上天皇の御世955(天暦9)年に創建。木野山山頂に奥宮があり、山麓に里宮が鎮座する。
白鳳時代に創建された寺院跡で、賀陽氏の氏寺であったと考えられています。発掘調査によって、塔などの伽藍配置の一部は明らかにまりましたが、全容は未解明です。
吉井川近くの台地上に所在する古代寺院。主要伽藍が判明し、遺構の残存状況は良好である。出土した瓦から中央との強い関係が想定され、古代美作国の政治情勢を示す上でも重要である。
出土遺物を陳列した展示室や収蔵庫をはじめ、遺物の化学的処理を行う木器・鉄器保存処理室、遺物整理室などがあります。
福山西北に独立した高さ164mの小山山頂部分にあります。東西の郭跡や,堀切・土塁状の遺構が見られます。鎌倉時代の終わり頃、備中の豪族 庄資房が初めて築城したと伝えられますが、室町時代中期に細川氏の守護代石川氏が約150年にわたって居城していたとみられてい…
雷除けに霊験あらたかなことから、別名を「雷神社」と呼ばれる鴨神社。毎年5月3日に行われる大祭は、雷除けの祭りとして古くから農家の信仰を集めてきました。
延喜元年(901年)に創建された真言宗の由緒ある古いお寺。約80枚の花鳥の彩色画からなる天井絵は、郷土の文人が寛政9年(1797年)に描いたもので、真庭市の指定文化財にもなっています。

瀬戸内市が誇る国際的な糸操り人形作家、竹田喜之助を顕彰するギャラリーです。市が保有する喜之助人形の企画展示の他、竹田人形座や喜之助関連の企画展示、TV作品や公演の模様を記録したDVDの上映も行います。(写真 中川正子)

室町時代から江戸時代にかけて備前焼の同業者が共同で使用した大規模な窯の一つです。伊部の西方、蕃山の山麓に位置し、窯跡を伝える記念碑があります。

開山は応永年間、最初は真言宗の寺院として建立され、その後、提山良山禅師が1679(延宝7)年に入山し、臨済宗永源寺派の末寺(大正14年発行・永源寺宗派図)となり今日に至る。
万燈山古墳出土品をはじめとする郷土の文化遺産や、人々の生活の歴史に関する資料を収集展示しています。

江戸時代初期の元和7(1621)年の創建としているが、詳しいことは分かっていません。本堂は江戸時代後期の天保2(1831)年に建築されたものです。
岡山市御津郷土歴史資料館は、旧御津町域から出土した考古遺物や民俗資料を展示し、岡山市域北部の歴史や民俗を概観できます。なかでも、全国的にも珍しい弥生時代のお祭りの様子を描いた新庄尾上遺跡出土の土器や原遺跡から出土した石鏃などの貴重な考古資料も展示し…

日常の中の美しい風景や作品の向こうに広がる身近な自然を感じられるように
岡山市東部、宝伝の沖約3kmに浮かぶ犬島は岡山市唯一の有人島です。犬島の集落に「日常の中の美しい風景や作品の向こうに広がる身近な自然を感じられるように」との願いを込め、2010年、企画展示を目的としたギャラリーが開館しました。アーティスティックディレクタ…

約165mの前方後円墳
約165mの前方後円墳で、操山丘陵の中央にあり上道平野を見渡すことができる絶好の位置にあります。1953年に発掘調査され、二つの竪穴式石槨が確認されました。どちらも石列と埴輪列による方形区画がめぐらされていて、出土品から4世紀末5世紀初頭の築造と考えられてい…
木造二階建の寄棟造、桟瓦葺の大型の洋風住宅で、明治24年(1891)に建てられました。1・2階とも正面に半円形のアーチを置き、扉口を設ける。円柱が並ぶ吹き抜けのバルコニーは、17~18世紀に西欧諸国の植民地時代の建築(コロニアル様式)を模しており、異国情緒をよ…

縄文から弥生時代の遺跡。特に縄文晩期にトチ、ドングリなどの食糧を貯蔵していた穴が残されており、当時の生活を知る貴重な遺跡として知られています。
横穴式石室を持つ3基の後期古墳と奈良時代の火葬墓からなる墳墓群で、日本の葬制、墓制を知るうえで貴重な遺構です。

600年以上の伝統をもつ特産「郷原漆器」について展示しています。郷原漆器は使えば使うほど輝きが増す魅力的な漆器。岡山県の重要無形民俗文化財に指定されています。予約すれば製作工程の見学も可能。

飛鳥時代に創建された寺院跡で、塔の心礎は往時の位置に現存しています。出土した軒丸瓦は2種類が確認されていて、第1類は県内最古の飛鳥様式で、第2類は吉備式と呼ばれるものです。
八塔寺山の深い緑の中、神亀5年弓削道鏡が開基したと伝えられ、今なお当時を偲ばせる寺院です。天台宗・本尊は十一面観音(行基作と伝う)境内裏の首なし地蔵は乳の出に霊験があり、池田光政寄進のつり鏡が現存する。
標高340mの山頂に築かれた山城で、北東を大手、南を搦手とし、南北に細長い曲輪を連ねています。東西12m、南北20mの平坦部の西側と北側に石垣が築かれています。
