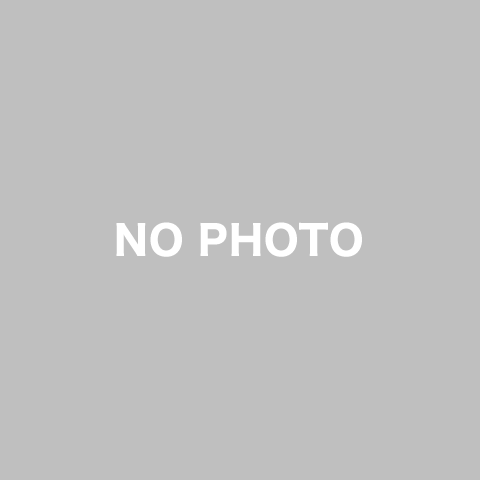幕末の岡山藩


幕末において、全国の大名たちは幕府を支持する「佐幕」か、天皇を支持する「勤王(尊王)」か、いずれかの選択を迫られました。岡山藩は勤王派として幕末維新の動乱期を立ち回ることになり、そこで懸念されたのが岡山藩の北に隣接する津山藩と備中松山藩がいずれも佐幕だったことです。不測の事態に備えて、北へ通じる主要な街道であった「津山往来」に台場を築く必要が生じたのです。
意外な場所にある「横井上お台場遺跡」

「なぜこんなところに?」というロケーションなのですが、それには理由があります。岡山市内と津山方面を結ぶ主要道として今は国道53号がありますが、「津山往来」は現代とは異なり、「半田山植物園」の脇から山を越えて「横井上お台場遺跡」のそばを通過するルートをとっていました。現在の様子からは想像もつきませんが、ここはかつて岡山の北と南をつなぐ要衝だったのです。
「横井上お台場遺跡」を図解で説明