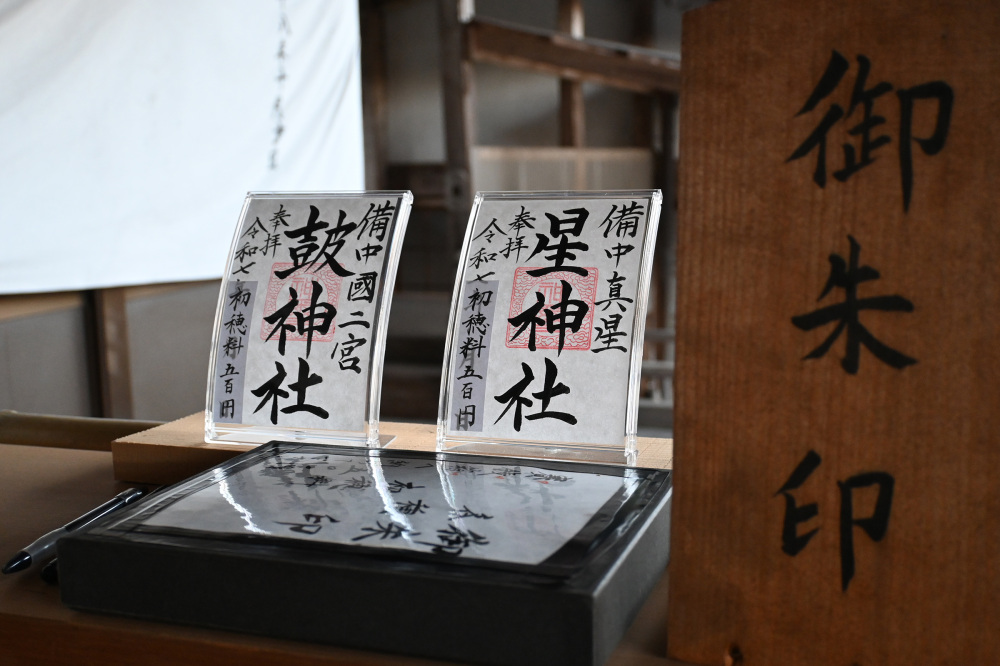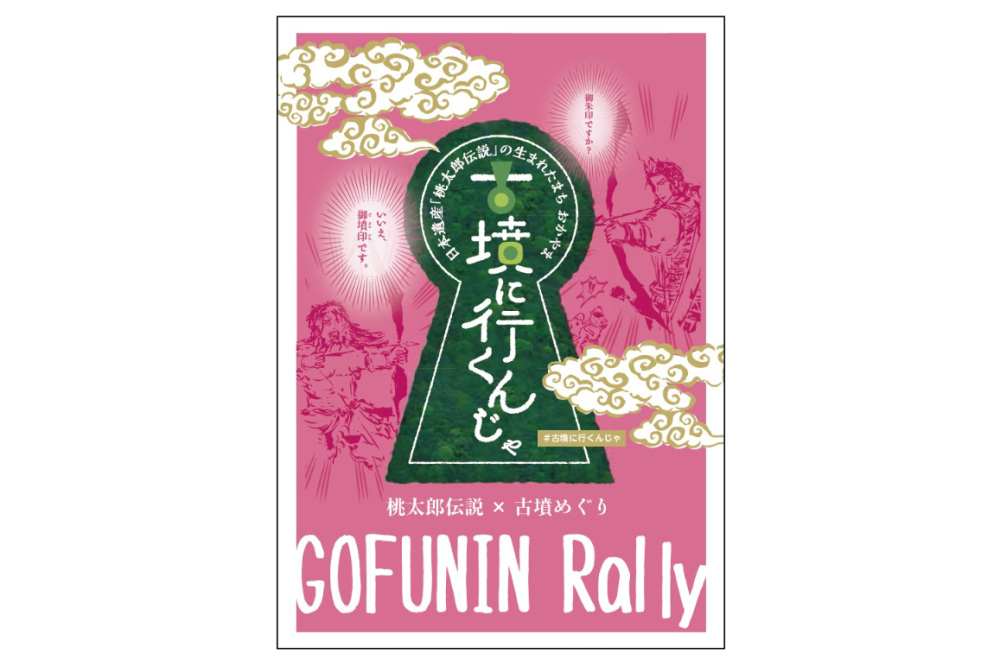岡山城の石垣を深掘り!市街地に残された石垣を探索しよう♪
現在の岡山城は城郭の中心部分であった「本丸」が公園として整備されていますが、かつては「二の丸」や「西の丸」などを持つ壮大な城郭でした。今回は岡山城の石垣の見どころや、市街地に残存する石垣について詳しく紹介していきます。
- ライター
- 田中シンペイ
- 掲載日
- 2025年6月25日
目次

岡山城の全容
岡山城の全容を図にしてみました。わかりやすいように、ランドマークとなるような現在の建物等の位置も示してあります。城址公園とされている「本丸」以外に、かつてはこれだけの領域が城として存在していたのです。
ちなみに、この図の左側(西側)には、さらに二重の水堀と土塁が築かれていました。江戸時代に幕府が諸大名に命じて提出させた詳細な城の絵図「正保城絵図 備前国岡山城絵図」によると、それら西側の防塁上には隅櫓や楼門などの構造物がまったく見られないため「惣構(そうがまえ)」(城下町を囲む防塁)と解釈して、今回の私の記事では城に含めないことにしました。
予備知識「石垣の進歩」
日本の城は戦国時代末期から江戸時代初期にかけて急激な発展を遂げました。例えば、今のパソコンやスマートフォンはすごいスピードで進化しているので、製造年が数年違うだけで性能が段違いだったりしますよね。それと同様に、当時の城も技術的な進歩がめまぐるしく、工事が行なわれた時期が少し違うだけで石材の加工方法や積み方などが大きく異なるのです。
加えて、石垣の技術者集団の個性による違いもありますので、城主が何度も変わって修築が繰り返された城は、多種多様な石垣が混在する状態となります。岡山城はその最たる例で、「石垣の博物館」と言われるほど多彩な石垣が城内にひしめいています。「本丸 中の段」では、発掘調査で出土した石垣を見ることができるような工夫も行なわれています。
本丸の見どころ
外下馬門(岡山県立図書館)
それでは城址公園の外に出て、市街地に残存する石垣を見ていきましょう。
写真は「岡山県立図書館」の敷地内に残る「外下馬門(そとげばもん)」の北側の石垣です。水堀を水盤で表現してあり、橋脚のあった場所も示されています。かつては長い木製の橋を渡った先に大きな城門がありました。
二の丸 東面(岡山県庁付近)
二の丸 対面所(林原美術館)
石山(旧本丸)
石山門
西手櫓(現存)
まとめ
「西の丸」の石垣は、ほぼ完存と言ってもよいくらい良好に残されています。そして何といっても貴重な現存建築である「西手櫓」の存在があります。「二の丸」も一部ではありますが往時の姿をとどめていて、そこには「林原美術館」など歴史スポットと親和性の高い魅力的な施設もあり、歴史好きの方であればこのエリアをめぐるのはとても楽しいと思います。
ここで少しだけ現状に苦言を呈するなら、貴重な城の遺構が「点」で存在し、まったく連続性がないということが言えると思います。現在、「西の丸」にあった小学校は廃校となり、市民会館やNHKの移転など、公園整備に向けた条件は整っています。遠方から岡山城を訪れた方が「本丸」だけではなく、これらの遺構をスムーズに見学できるように、点を線に、線を面にしていく整備が望まれます。それまでは、宝探しの気分で現地をめぐってみるのも一興かと思います。
地図
- 岡山城(烏城)
- 岡山県立図書館
- 林原美術館
Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。