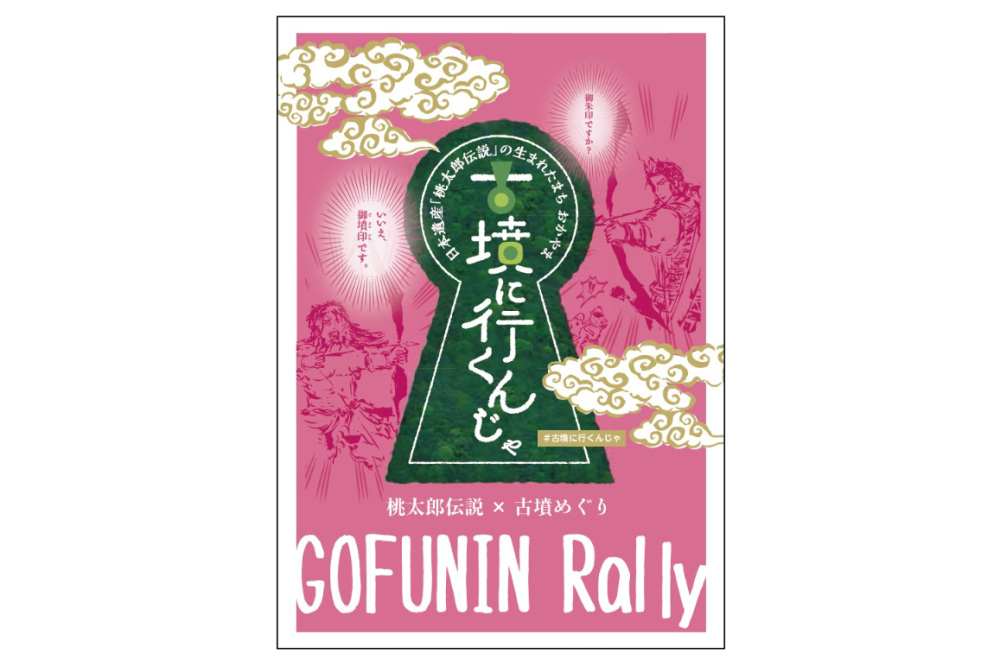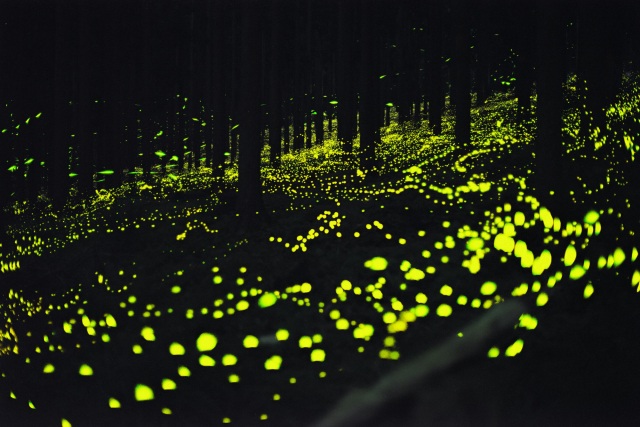【牛窓歴史散歩】製塩の歴史と牛窓。塩田跡の現在をたずねて(瀬戸内市)
瀬戸内市の牛窓は古来より海上交通の要衝として栄えましたが、製塩業もその繁栄の源のひとつでした。今回は錦海塩田跡を中心に、牛窓ならではの美しい風景をご紹介したいと思います。
- ライター
- 田中シンペイ
- 掲載日
- 2025年8月25日

塩と牛窓
製塩の歴史
塩は狩猟や採集で生活していたころの人類には、特に必要なものではありませんでした。農耕の発展によって穀物や野菜が食料の主体になると、植物に含まれるカリウムとのバランスをとるためにナトリウム(塩の主成分)が必要となり、生理的な必要性から塩味を好むようになったと考えられています。
塩を作る際には、海水をそのまま煮詰めるより塩分濃度を高めておいてから煮詰めたほうが効率が良いため、海水を太陽光で蒸発させて塩分濃度を高めておくための施設が「塩田」です。内海に面し、晴天率が高くて温暖な岡山県は塩を作るには最適の場所でした。
私の過去の記事で牛窓には古墳が多いというお話をしたことがありますが、古来より塩は重要な交易品であり、牛窓の人々が製塩で大きな富を得ていたことも牛窓に古墳が多い理由のひとつと考えられています。(写真は阿弥陀山古墳群)
師楽
錦海湾の南東部に「師楽(しらく)」という名前の小さな入り江があり、干潮時には干潟が姿を現すなど自然な姿の海岸が残されています。
この地で発見されたことから命名された「師楽式土器」という特殊な土器があります。海水を煮詰めて塩を作るための製塩土器の一種で、古墳時代にこのあたりで大量に製作され、後世の「備前焼」の発展にも関係していると考えられています。牛窓エリアは海上交通の要衝であると同時に、塩や土器の特産地でもあったのです。
長浜
錦海湾の最奥部に、大正時代に築かれた締切堤防が残されています。「安田堤防」と呼ばれ、約100ヘクタールの干拓地が造成されました。それが現在の長浜地区で、キャベツや白菜などの重量野菜を育てる畑が整然と並ぶ長閑な風景が広がっています。
錦海湾堤防
錦海ハビタット
まとめ
紹介したスポットの場所(地図)
- 錦海堤防
- 師楽
- 長浜
- 道の駅 一本松展望園
Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。