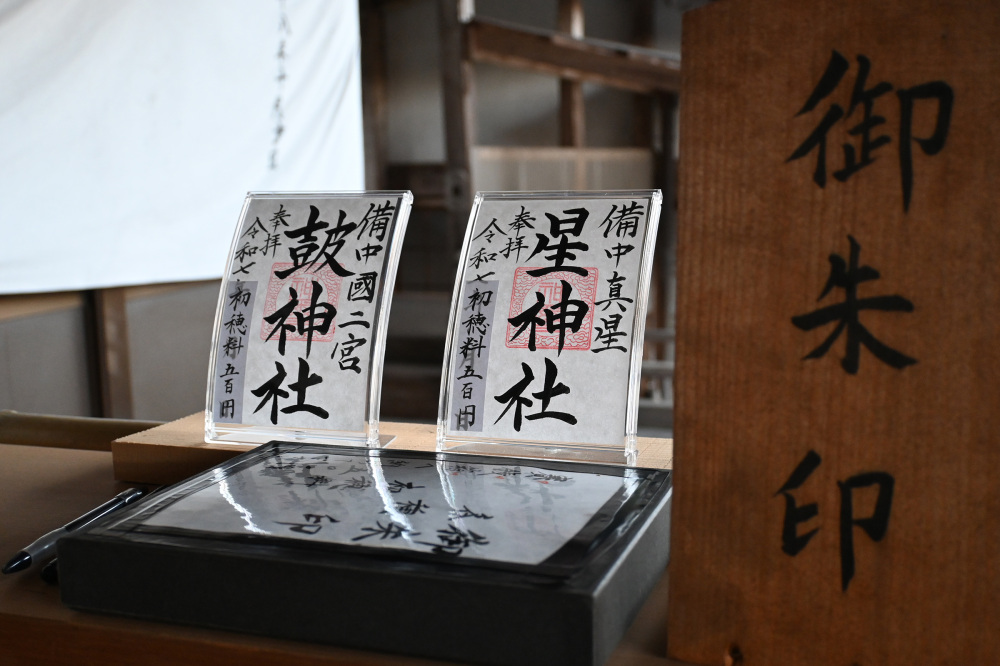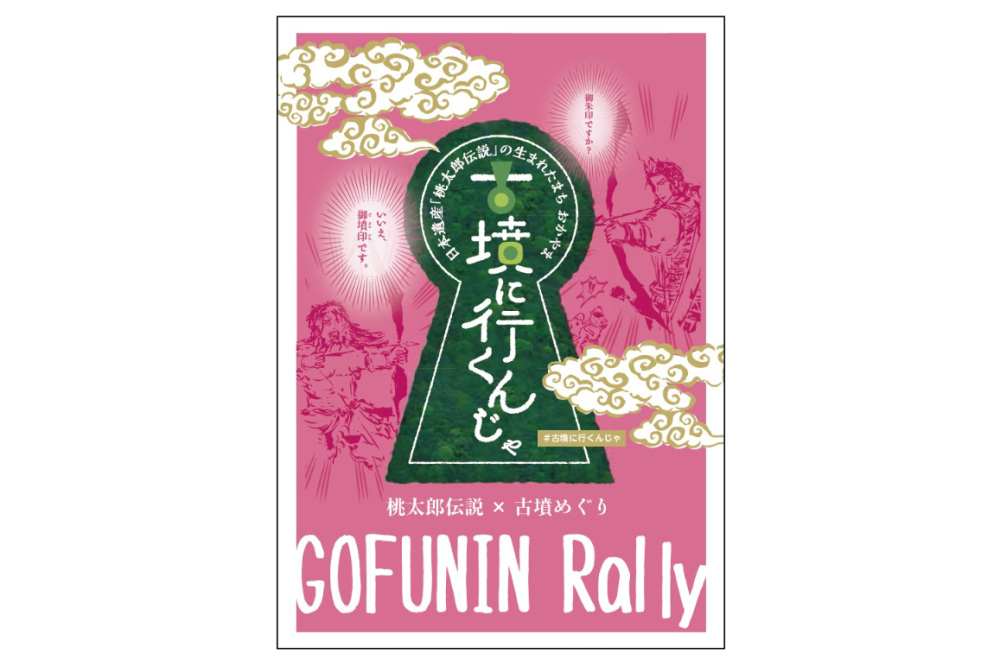本殿がない!? 岡山県で一風変わったご神体の神社を参拝してみよう!(備前市・総社市)
「え、これが神社のご神体⁉」と思わず驚いてしまう、岡山県内にある本殿を持たない神社を2つご紹介します。
- ライター
- 田中シンペイ
- 掲載日
- 2025年11月20日

田倉牛神社(備前市)
「田倉牛神社」は(たくらうしがみしゃ)と読みます。江戸時代には農耕用に飼われていた牛馬の健康を祈願する神様でしたが、現在では病気平癒のほか、家内安全、商売繁盛など、さまざまなご利益のある神社として多くの方が訪れています。
一見すると普通の境内ですが、社殿は見当たりません。ご神体は奥にある石段をしばらく登った先に鎮座しています。
かつては「牛頭天王」が祀られていた神社で、鳥居の扁額には「野上牛頭天王宮」とあります。
牛頭天王とは
「牛頭天王(ごずてんのう)」は、古代インドの仏教寺院「祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)」の守護神であるとされ、本来は仏教の神様です。その信仰が複雑に変化し、神仏習合(日本古来の神と仏教の神の融合)によってスサノオノミコトと同一の存在とみなされました。やがて疫病や災いを祓う「祇園信仰」として全国に広まり、京都の「祇園祭」で知られる「八坂神社」が特に有名です。明治以降は、政府による神仏分離政策によって神社から仏教的な要素が排除され、神仏習合の神社では祭神や名称の変更が行なわれました。
ご覧ください、こちらがご神体です!
といっても、この写真ではよくわからないですよね…。
近くで見ると、無数の備前焼製の牛の山であることがわかります。ほとんど見えませんが中央にある牛の石像がご神体とされています。それにしてもインパクトがすごい!
この神社は参拝方法がとても変わっています。まず、備前焼でつくられた牛の像(参道で購入可能)をお供えして祈願し、以前に誰かがお供えした牛の像1体を選んで家に持ち帰り、願いが成就した際にはお礼としてもう1体を加えて2体をお返しします。このようにして、これまでに奉納された数は30万体にのぼるとも言われています。ひとつひとつの牛に誰かの願いが込められているんですね。
鳥居の奥に見えているのがご神体へ向かう石段なのですが、画像からも想像できるとおり少々キツい角度になっています。脇には急峻な石段を登れない方のための祠が用意されていて、こちらに奉納することもできます。
例年、1月5日の大祭には多くの参拝者が訪れますが、普段はとても静かで落ち着いた場所です。ときおり山陽本線が参道の前を通過して、周囲に響き渡る警報機の音が何とも言えない郷愁を誘います。
こちらが家に持ち帰った備前焼の牛さんです。とてもかわいらしいですね。願いが成就して再び「田倉牛神社」を訪れる日が楽しみです。
石畳神社(総社市)
続いてご紹介するのは、巨大な岩をご神体とする「石畳神社(いわだたみじんじゃ)」です。高梁川のほとりに位置していて、拝殿はありますが本殿はありません。
拝殿の脇を抜けて数百メートル登った先にご神体の岩が鎮座しています。急峻なうえに少し荒れた道なので、スニーカーなどの歩きやすい靴で行ってください。鳥居のそばには、親切なことに杖が用意されていました。
こちらがご神体です!大きな岩が、まるで人為的に積み上げられたかのように見えます。
これは、いわゆる「磐座(いわくら)」と呼ばれる古代信仰の貴重な実例です。この位置からは上部しか見えていませんが、全体はもっと巨大です。断崖絶壁になっていて危険なので、これ以上先に立ち入ることはできません。
磐座とは
「磐座(いわくら)」とは日本の原始的な祭祀形態のひとつで、降臨した神がそこに宿ると考えられた岩のことです。神社のような神殿が発達する以前の非常に古い祭祀形態で、現在でも神社の境内や背後の山にある“しめ縄の張られた岩”は磐座信仰の名残です。また、岩を配置して作られた神域を「磐境(いわさか)」と言います。
下には高梁川と大きな橋が見えています。参拝を済ませたら、橋まで移動して磐座の全体を見てみましょう。
高梁川に架かる「豪渓秦橋」から見たご神体の全容です。すごい迫力ですね!高さは60mもあるそうで、20階建てのビルに相当します。昔の人々が神の存在を感じたこともうなずけます。高梁川が大きくカーブする場所なので、治水を祈願する祭祀が行なわれたと考えられていますが、御祭神は「経津主神(ふつぬしのかみ)」という刀剣の神様です。どのような関わりを持つのか不思議ですが、「経津主神」が岩の神様から生まれたことに由来しているのかもしれません。また、所在地である総社市“秦”(はだ)は、多くの謎を秘めた古代の氏族「秦氏」とゆかりの深い土地で、古墳や寺院跡などさまざまな史跡が残されています。
この地点では高梁川の川幅が狭くなっているため、それまで使われていた道が洪水で失われて、やむなくご神体の下にトンネルが作られました。工事の際には反対意見も出たそうで、暴れ川のほとりで生活する人々にとって苦渋の選択だったことが想像されます。
古来より「石畳」には「険しい」「容易にたどりつけない」というイメージがあったのでしょうか、高嶺の花へ向けた恋心を「石畳」になぞらえた歌が『万葉集』に収録されています。比喩として使われるほど、当時は広く知られた存在だったことがうかがえます。
『万葉集 巻七 作者不詳』
石畳 さかしき山と知りながら 我は恋しく 友ならなくに
[個人的現代語訳]
石畳のようにおそれ多く、険しい道のりだと分かっているけれど、私はあなたに心を寄せています、とくに親しいわけでもないのに
「石畳神社」は、さまざまな古代のロマンにあふれた場所です。ぜひ一度足を運んでみてください。
まとめ
岡山県内には多数の磐座が存在していて、全国的に見ても多い方だと言われています。大概は険しい山の上にありますが、著名な寺社の敷地内にも磐座が残されていることがあります。訪れた際には、そういった点にも注目してみてください。
■吉備津彦神社
神社の背後に位置する「吉備の中山」には複数の磐座があり、夏至には磐座と本殿を結んだ延長線上に太陽が昇ると言われています。
■最上稲荷(最上稲荷山妙教寺)
神仏習合が特別に認められた“仏教の流れをくむ神社”として広く知られ、奥の院へ向かう途中には磐座「八畳岩」があります。
■阿智神社
倉敷美観地区に所在する神社ですが、かつては瀬戸内海に浮かぶ島で、境内には複数の「磐座」や「磐境」が残されています。
紹介した神社の場所(地図)
- 田倉牛神社
- 石畳神社
Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。