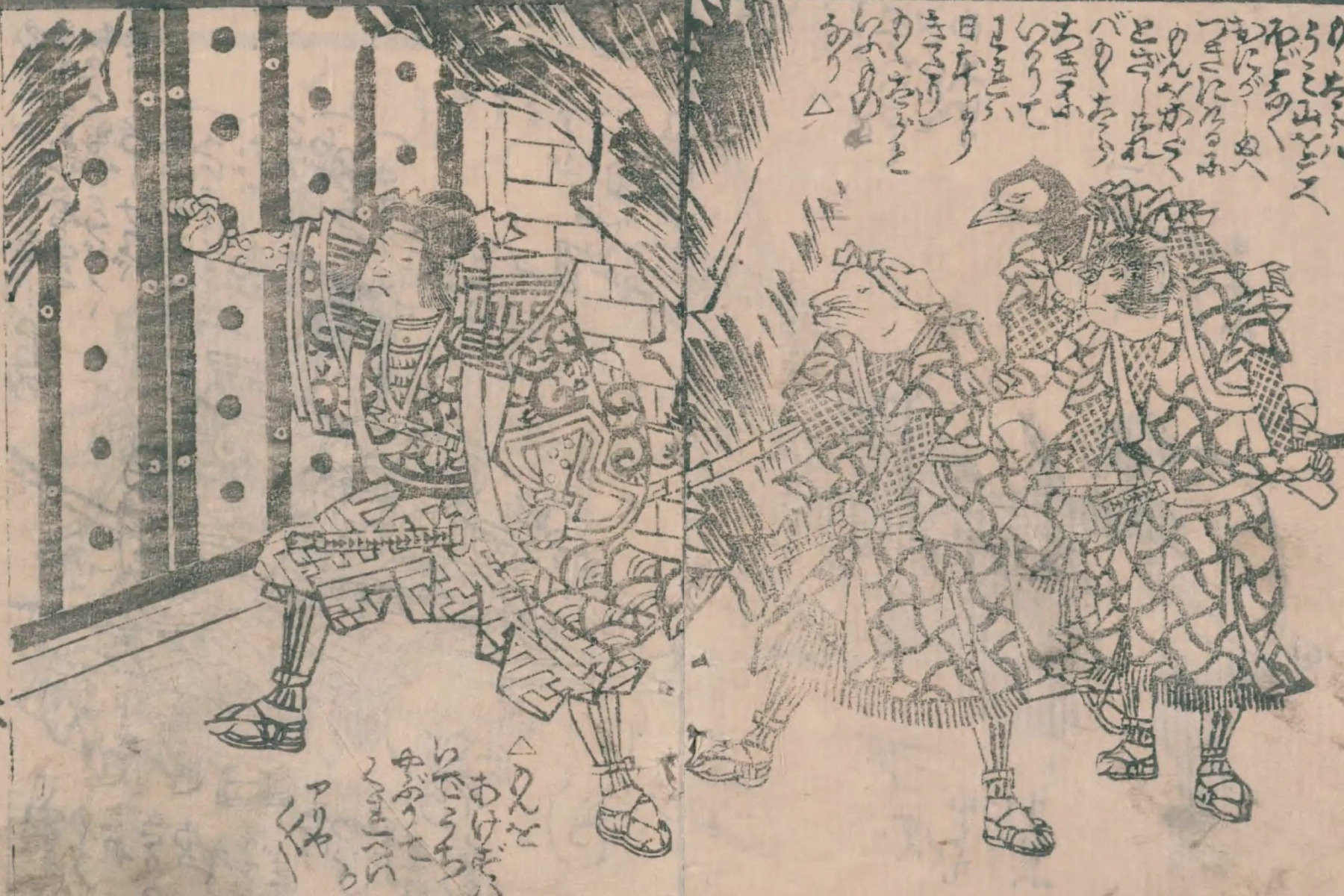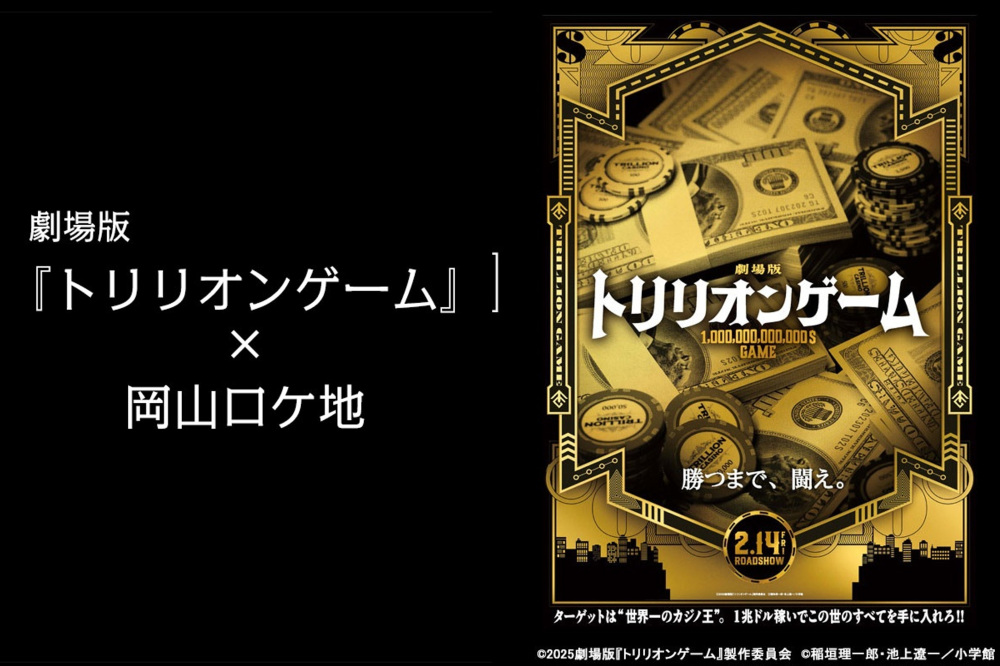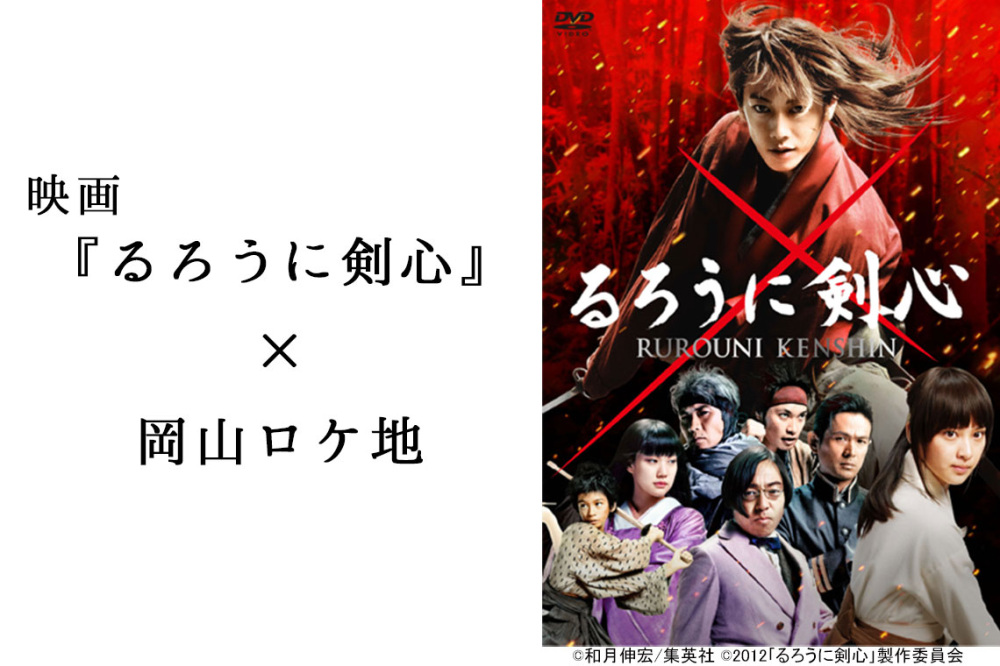桃太郎ってどんな話?物語の原型となった温羅伝説や岡山との深い関係性を徹底解説!
誰もが一度は聞いたことがある昔話「桃太郎」。実は、そのルーツが岡山にあるとご存じでしたか?
この記事では、物語の原型となったとされる温羅退治伝説の紹介から、桃太郎伝説の解説、そして桃太郎にちなんだスポットやお土産の紹介まで、桃太郎に関連する情報を幅広くご紹介します!
画像(右):「桃太郎 2巻 (赤本昔はなし)」国立国会図書館
目次

桃太郎伝説の原型「温羅退治」とは?~鬼と英雄、驚きの物語~
岡山は「桃太郎伝説の生まれたまち」として2018年に日本遺産に認定されました。
この背景には、古代から吉備(=昔の岡山周辺)の地で語り継がれてきた「吉備津彦命(きびつひこのみこと)による温羅(うら)退治」の伝説があり、後に桃太郎の原型になったといわれています。
物語の中で「鬼」と恐れられた温羅は、一丈四尺(約4.2m)にも及び、虎や狼のように爛々と輝く両眼、燃えるような赤い髪と髭を持つ異形の姿で、備中国新山(現在の総社市)に「鬼ノ城(きのじょう)」と呼ばれる居城を構え、人々を苦しめる悪事を重ねていました。
温羅の悪事に苦しみ、困った人々が大和朝廷に訴えたことにより、弓の名手である吉備津彦命が、大軍を率いて吉備の地へ派遣されることになりました。
吉備津彦命は、まず吉備の中山(きびのなかやま)に陣を構え、温羅の矢を防ぐための巨石の楯(現在の楯築遺跡(たてつきいせき))を築きました。
次に、岩に矢を置いて(現在の矢置石)温羅に向けて放つと、温羅も居城である鬼ノ城から岩を投げ返し応戦しました。
このとき、互いに放った矢と岩が空中で何度もぶつかり合い、谷に落ちていったとされます(現在の矢喰宮)。
互角の戦いが続く中、吉備津彦命が渾身の力を込めて一度に二本の矢を放つと、そのうちの一矢がついに温羅の左目を射抜きました。
傷を負った温羅は、たまらず雉(きじ)に化けて山中に逃げ込みますが、吉備津彦命も鷹に姿を変えて追跡します。
さらに温羅は、鯉に化けて血で真っ赤に染まった川(現在の血吸川)に逃れましたが、吉備津彦命も鵜に変身して温羅を捕らえ(現在の鯉喰神社)、見事鬼退治を果たしたと伝えられています。
一方で温羅は、朝鮮半島から先進的な製鉄技術や造船技術をもたらし、吉備の国を繁栄に導いた人物であり、その功績によって民衆からは「吉備冠者(きびのかじゃ)」として親しまれていたという説もあります。
彼が「鬼」とされたのは、大和朝廷が地方勢力である吉備王国を統合する際に、その強力な在地勢力を「悪者=鬼」として位置づけ、征服を正当化するためだったのかもしれません。
百済から渡来した王子だった可能性も!?
温羅の本当の姿は、古代朝鮮の百済(くだら)から渡来した王子であったとも言われており、古代吉備の地にもたらされた「文化の使者」であった可能性も、近年指摘されています。いずれにせよ、大和朝廷が警戒する一大勢力が吉備王国にあったことがうかがえます。
※写真は岡山駅西口にある温羅の像

「うらじゃ」鬼のメイクで温羅に感謝!
岡山市中心部で毎年夏・秋・冬に開催される「おまやま桃太郎まつり」は県下最大級のお祭りです。
夏に開催される「おかやま桃太郎まつり」では、8月の第3土曜日と日曜日に「うらじゃ」を開催。
温羅伝説をモチーフに、鬼のメイクを施した踊り子たちが華麗な演舞を繰り広げます。
鬼を退治する桃太郎ではなく、鬼が主役のこのお祭りからは、吉備国の発展に大いに貢献した英雄への感謝の気持ちが感じられます。

伝説の舞台を巡る~日本遺産「桃太郎伝説」ゆかりの地スポット①~
この伝説の舞台となった場所は、現在も語り継がれており、実際に訪れることができます。
- 鬼城山(鬼ノ城)
- 総社市にある標高約400mの山に築かれた、温羅の居城であったとされるもの。実際は歴史書に記載がない謎の山城で、大和朝廷によって国の防衛のために築かれたと推測されています。
※日本100名城 
- 詳細を見る
- 矢置岩
- 吉備津彦命が温羅退治の際に矢を置いたと伝わる吉備津神社の正面石段脇に位置する巨石。神への奉献物である矢を置く供物台石として使われ、古代から岩石信仰の対象として崇められており、江戸時代に描かれた境内絵図にも記録されています。

- 詳細を見る
- 楯築遺跡
- 吉備津彦命が温羅からの攻撃を防ぐために築いた「楯」と伝えられる史跡で、日本最大級の弥生墳丘墓です。墳丘頂上には5個の巨石が円形に配置され、祭祀や天体観測との関連も指摘されるなど、その用途には謎が残ります。

- 詳細を見る
- 矢喰宮(矢喰岩)
- 吉備津神社から放たれた吉備津彦命の矢と、鬼ノ城から投げられた温羅の岩が空中で激突し、落下した場所に建立されたと伝わる宮です。境内には「矢喰岩」と呼ばれる大小4つの巨石群が残され、温羅が投げたとされる岩の一部と言われています。

- 詳細を見る
- 血吸川
- 吉備津彦命に追い詰められ、ついに矢で射られた温羅の血が、この川に流れ込み、川一面を赤く染めたことから、この名がついたとされています。温羅が雉から鯉に化けて逃げ込んだのもこの川であり、物語クライマックスの重要なスポットです。

- 詳細を見る
- 鯉喰神社
- 温羅が鯉と化して逃げた際、吉備津彦命が鵜に変身してその鯉を捕食し、ついに温羅を退治したとされる、最終決戦の舞台となった場所です。現在もその伝説を伝える神社には、社殿の瓦屋根に鯉の姿があります。

- 詳細を見る
- 造山古墳
- 全長約350mを誇る全国第4位の前方後円墳です。5世紀初頭に築造され、近畿の天皇陵にも匹敵する規模感は、古代吉備の強大さを示しています。立ち入り可能な古墳としては最大なので、ぜひ現地に訪れて、その巨大さを肌で体感してください。

- 詳細を見る
- 両宮山古墳
- 全長206mの前方後円墳で、5世紀後半に築造され、二重の周濠がともなっていたと言われています。大規模古墳では珍しく「葺石(ふきいし)」や「埴輪(はにわ)」が一切発見されていないという謎を秘めています。

- 詳細を見る
【2026年】吉備津神社「矢立の神事」
吉備津神社で毎年1月3日に行われる伝統的な神事で、「矢置岩」に弓矢を並べて清めのお祓いを行います。その後、天に向けて四方向に矢を放ち、邪悪なものや災禍を祓い清め、国家の平和、人々の無病息災、五穀豊穣、そして招福を祈願します。

退治された鬼・温羅のその後の二つの結末
温羅退治の物語には、実は二つの異なる結末が伝えられています。
これらこそが、桃太郎伝説の奥深さ、そして古代吉備の歴史的背景を物語る重要なポイントです。
【物語1】吉備津神社に伝わる「唸る首」の物語
吉備津神社に伝わる「吉備津宮縁起」によれば、吉備津彦命は温羅との戦いに勝利した後、温羅の首をはねて白山神社の首塚(くびづか)にさらしたとされます。しかし、何年経っても温羅の首は不気味な唸り声を上げ続け、その声は近隣に鳴り響きました。
そこで吉備津彦命は、唸り声がやまない温羅の首を、吉備津神社の御竈殿(おかまでん)の釜の下深くに埋めました。それでも唸り声は13年間もおさまらなかったといいます。
ところがある夜、吉備津彦命の夢枕に温羅が現れ、自分の妻である阿曽媛(あそひめ)がこの釜を使って米を炊くようにすれば、自身が吉備津彦命の使いとなり、釜の音で世の吉凶を占うと告げました。吉備津彦命が温羅の言う通りにすると、唸り声は「ヴォーン、ヴォーン」と聞こえる釜の音に変わり、吉凶を告げるようになったのです。
この故事は、現在も吉備津神社で行われている「鳴釜神事(なるかましんじ)」として継承されています。
神事では、過去に災いをもたらした温羅が、死後には地の吉凶を告げる使いとなったという、和解と鎮魂の物語を示しています。
また、吉備津神社の艮御崎宮(うしとらみさきぐう)には温羅が祀られており、温羅の顔を思わせる鬼面が伝わっています。
【物語2】吉備津彦神社に伝わる「家来となった温羅」の物語
もう一つの温羅伝説は、吉備津彦神社に伝わる「吉備津彦神社縁起」に記されています。この縁起では、吉備津彦命との激しい戦いの末、温羅はついに観念し、吉備津彦命にひざまずき「命だけは助けてほしい。あなたの家来となって吉備の国を良い国にしてみせる。私が作った宝物の鉄器の道具なども差し上げます」と懇願します。
吉備津彦命は温羅の願いを聞き入れ、彼を家来として、共に吉備の国を治めることにしました。温羅はその後、吉備津彦命に忠実に仕え、武力に秀で、志も立派であったため、吉備の中山にある小丸山に艮御崎神社(うしとらみさきじんじゃ)として祀られるようになったと伝えられています。この伝承の最大の特徴は、温羅が「殺されていない」点にあり、吉備津宮縁起とは大きく異なっています。
このように、温羅退治の物語には「征服と鎮魂」、あるいは「和解と共存」という二つの異なる側面が見て取れます。これは、古代吉備が単に大和朝廷に屈服したのではなく、その後、複雑なかたちで統合されていった過程を物語っており、伝説には多くの意味が込められていることがうかがえます。この奥深さこそが、今日まで多くの人々を惹きつけてきた理由なのです。
伝説の舞台を巡る~日本遺産「桃太郎伝説」ゆかりの地スポット②~
- 吉備津神社
- 岡山市北区吉備津に位置し、国宝に指定された本殿・拝殿は、全国でも唯一の建築様式「吉備津造」を採用。本殿から続く全長360mにわたる長い廻廊は一見の価値がある歴史的建造物です。伝説では吉備津彦命の温羅退治の拠点とされ、境内には温羅の首が埋められていると伝わる御竈殿があります。

- 詳細を見る
- 白山神社の首塚
- 岡山市北区首部にある小さな神社の境内に、「温羅の首塚」と伝えられる塚があり、首部(こうべ)の地名はこれに由来していると言われています。参道の石段を登ると、お尻を上げた姿勢の珍しい「構え獅子」が参拝者を迎え、他の神社では見られない独特の雰囲気を醸し出しています。

- 詳細を見る
- 吉備津彦神社
- 吉備津神社同様に吉備津彦命を祀る備前国一宮。岡山市北区一宮に位置し、背後にある吉備の中山は古代より神の降臨地とされてきた神聖な場所です。夏至には太陽が正面鳥居の真正面から昇り、神殿の御鏡に入るという神秘的な現象が起こることから、古代太陽信仰の聖地として崇められ“朝日の宮”とも呼ばれています。

- 詳細を見る
桃太郎物語の要素に見る岡山との深いつながり
さて、ここからは桃太郎の話へと移ります。
桃太郎といえば、多くの人が「桃から生まれた」という場面を思い浮かべるでしょう。この物語の象徴ともいえる「桃」こそが、岡山と桃太郎伝説を深く結びつける最初のポイントになります。
岡山県は、温暖で晴れの日が多く、昔から桃の栽培がさかんに行われてきました。特に「清水白桃」などの高級な桃は、今では岡山の名物として全国的に知られています。
さらに驚くべきことに、桃は昔から「魔除けの道具」として使われてきたという歴史背景があり、弥生時代に遡る上東遺跡からは、なんと9,606個もの桃の種が出土しており、約2,000年前から岡山では桃が神聖な深い意味を持つものだったことが伺えます。
桃太郎が「桃」から生まれ、鬼を退治して魔を払うという物語には、まさにこうした地域の歴史や文化が深く関わっているのです。岡山が豊かな桃の産地であるという現実が、桃太郎の物語にリアリティと奥行きを与えていると言えるでしょう。
「お腰につけたきびだんご、ひとつ私にくださいな~」
この歌で知られる「きびだんご」は、桃太郎が犬・猿・キジを仲間にするときに渡す印象的な食べ物で、こちらも岡山と桃太郎伝説をつなぐ重要なキーワードです。
「きびだんご」の名前は、岡山の旧国名「吉備(きび)」に由来するとされており、桃太郎が持っているアイテムがそのまま岡山の地名と結びついているのです。
また、「黍(きび)」という穀物も、昔から岡山でよく作られていたと伝えられています。現在も岡山を代表する銘菓として親しまれている「きびだんご」は、江戸時代には吉備津神社の門前で売られていたという記録もあります。
物語の中で「きびだんご」は、単なる食べ物ではなく、桃太郎が動物たちと仲良くなり、一緒に鬼退治に向かうための「きずなをつなぐもの」として大切な役割を果たしています。これは、古代の勢力争いにおいても、武力だけでなく、交渉や物の取引を通じて信頼関係を築いていたことを思わせるエピソードでもあり、桃太郎のリーダーシップの深さを感じさせる場面でもあります。
ただし、研究者の中には、昔の桃太郎物語では「きびだんご」ではなく「とう団子」など別の名前で呼ばれていたという説や、岡山名物としての「吉備団子」は江戸時代の終わりごろに桃太郎にちなんで売り出されたという指摘もあります。
それでも「きびだんご=吉備団子」というイメージが、多くの人に岡山を桃太郎のふるさととして強く印象づけてきたことは間違いありません。今では岡山の観光や名物のPRにも欠かせない存在となり、地域のブランドづくりにも大きく貢献しています。
桃太郎の家来として知られる犬・猿・キジ。この3匹の動物も、岡山との深いつながりがあります。
桃太郎のモデルとされる吉備津彦命が、鬼とされる温羅と戦ったとき、彼に仕えていた家臣の中に、犬・猿・キジの元になったとされる人物がいました。たとえば、犬のモデルは犬飼武(いぬかい たける)、キジは留玉姫(とめたまひめ)、猿は楽々森彦(ささもりひこ)といった人物たちです。
さらにおもしろいのは、こうした名前に関係する「犬飼」などの地名が、今でも岡山県内に残っていることです。これは、桃太郎の物語がこの地域の伝説や歴史に深く根づいていることを示しています。
また、民俗学的な視点からは、これらの動物たちは、吉備津彦命が吉備の地をおさめるときに協力した古代の有力な氏族や、その土地に祀られていた神様をあらわしているのではないか、とも言われています。桃太郎に家来として仕えるという形で、かつて大和朝廷と対立していた吉備の勢力が、しだいに統合されていった歴史を象徴しているという解釈です。
このように、「桃」「きびだんご」「家来たち」といった桃太郎の物語に出てくる要素は、ただの昔話の設定に留まらず、岡山の歴史的背景、地理的特徴、そして文化と密接に結びついています。こうした深いつながりを持つ桃太郎伝説が、今も息づいているからこそ、岡山は「桃太郎伝説の生まれたまち」として日本遺産に認定されることになりました。みなさまも物語の舞台を、ぜひ実際に歩いて感じてみてください。
お土産はやっぱりこれ!種類も豊富な「きびだんご」
岡山土産といえば、やはり外せないのが桃太郎伝説にちなんだ「きびだんご」!
老舗から新進気鋭まで、さまざまなメーカーが個性豊かなきびだんごを作っています。
この記事では、3つを厳選して紹介しますので、もっと知りたい方は詳細な記事をご覧ください。
- 廣榮堂「元祖きびだんご」
- 創業1856年、きびだんごの元祖として知られる廣榮堂。もち米に砂糖、水飴を加えて丁寧に練り上げ、黍を加えた伝統製法で作られる、上品で素朴な甘さと、もちもちとした食感が特徴です。黒糖やきなこ、抹茶、白桃などの味も展開しています。

- 敷島堂「元祖マスカットきびだんご」
- 岡山県産マスカットの産地ならではの逸品!敷島堂が独自の技術で加工したマスカット果蜜を、きびだんごの中に閉じ込めた革新的な商品です。一口噛むと「とろ~り」とマスカット果蜜があふれ出し、甘酸っぱいフルーティーな味わいが楽しめます。

- 中山昇陽堂「塩チョコきびだんご」
- 岡山伝統のきびだんごを現代風にアレンジ!従来のきびだんごにチョコレートと塩をプラスした新感覚の味わいで、甘じょっぱさがクセになります。他にも「ちび桃きびだんご」など、小さくかわいい袋タイプの商品などユニークな商品を多数展開しています。

岡山で楽しむ!桃太郎テーマの楽しいスポット
桃太郎の故郷である岡山には、桃太郎をテーマにした楽しいスポットがたくさんあります。
大人から子供まで楽しめる、記念撮影にもぴったりな場所を3つご紹介します!
- 桃太郎のからくり博物館
- 館内には桃太郎伝説に関する貴重な資料や人形が展示されているだけでなく、洞窟探検「鬼ヶ島」などの体感型アトラクションも組み合わされた、他では体験できないユニークな博物館です。

- 詳細を見る
- 桃ボート
- 岡山城と岡山後楽園の間を流れる旭川で楽しめるのが「桃ボート」!大きな桃の形をしたかわいらしいボートに乗って、まさに「どんぶらこ、どんぶらこ」と桃太郎気分を存分に味わえます。

- 詳細を見る
- 岡山桃太郎空港
- 岡山の空の玄関口!2021年に復活した初代桃太郎像が空港利用者を出迎えてくれます。飛行機を利用しなくても、岡山名物のグルメやショッピングを楽しむのにおすすめです。

- 詳細を見る
岡山といえば桃太郎!一緒に撮影できるおすすめ桃太郎像 5選
JR岡山駅前の「岡山の顔」とも言える桃太郎像から、空港の初代桃太郎像、桃太郎大通りの可愛い銅像群まで、それぞれ異なる魅力を持つ桃太郎像の撮影スポットを地元ライターが詳しく解説しています!

岡山の桃は絶品!ご当地カレーにも桃!
くだもの王国として知られる岡山の桃は、上品な甘さとなめらかな食感で全国的に有名です。6月下旬~8月にかけて、早生桃の「はなよめ」や「日川白鳳」から始まり、岡山白桃の代表格「清水白桃」、岡山生まれの大玉で高糖度の「おかやま夢白桃」、岡山白桃の終盤を飾る「白麗」など、さまざまな品種が旬を迎え、観光農園でも桃狩り体験が楽しめます。
そして今話題なのが、桃農家が自宅で楽しんでいた「白桃のチャツネ」を隠し味にしたご当地グルメ「岡山カレー」!スパイシーなカレーに桃の上品な甘さとコクがプラスされ、まろやかな仕上がりに。岡山市内40以上の店で味わうことができ、新たな岡山名物として注目を集めています。
観光の際は、桃を使ったスイーツやお土産、桃狩りや岡山カレーなど、岡山の桃を存分にお楽しみください!
伝説息づく「桃太郎のまち」岡山へ
古代から語り継がれる温羅伝説が今も息づく「桃太郎のまち」岡山は、訪れる人々の想像力をかき立てる魅力に満ちています。
吉備津神社や鬼ノ城などを巡れば、昔話が現実と重なる感動に出会えるでしょう。
あなたもぜひ、桃太郎の足跡を辿る旅に出かけてみませんか?
岡山桃太郎伝説MAP
- 鬼城山(鬼ノ城)
- 矢置岩
- 楯築遺跡
- 矢喰宮(矢喰岩)
- 血吸川
- 鯉喰神社
- 造山古墳
- 両宮山古墳
- 吉備津神社
- 白山神社
- 吉備津彦神社
- 桃太郎のからくり博物館
- 桃ボート
- 岡山桃太郎空港
Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。








![画像:「[お伽噺]桃太郎鬼ヶ島でん」国立国会図書館](/lsc/upfile/articleDetail/0000/1056/1056_1_l.jpg)
![画像:「[お伽噺]桃太郎一代記」国立国会図書館](/lsc/upfile/articleDetail/0000/1057/1057_1_l.jpg)